ストレスチェック実践 -個人・メンタルヘルス面談-
✅ストレスチェックで用いる項目について
必要項目
ストレスチェックでは
①心の心理的な負担の原因に関する項目
②心理的な負担による自覚症状に関する項目
③他の労働者による支援に関する項目
以上3領域の質問を含めば様式の指定はない。ないが
職業性ストレス簡易調査票(57項目)
→厚労省が公開しているチェックリストを用いるのが無難。
参考:厚生労働省 職業性ストレス簡易調査票(57項目)
項目を絞った簡易verもある
不適当な項目
ストレスチェックでは上記項目を含めば指定様式はないものの、
・性格検査
・希死念慮
・うつ病検査
などは追加する項目として不適当とされる。
これはストレスチェックの目的がうつ病等の1次予防であり、上記のような項目はその目的にそぐわないため。
✅高ストレス者の定義
高ストレス者の定義としてっ用いられるのが
①『心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目』の評価点数の合計が高いもの
②『心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目』の評価点数の合計が一定以上かつ『職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目』および『職場における他のの労働者による当該労働者の支援に関する項目』の評価点数の合計が著しく高い者。
実際の点数は用いるストレスチェックの項目によるが
✅結果の返却
ストレスチェックの結果は個人に返却される
多くの場合は外注(健康診断の結果などと合わせて)することになり
数値や図表を用いてストレスの特徴や傾向が記載されてくる。
結果は原則事業者には提供されず、提供の際には結果を本人が確認したあとで文書などによる個別んお本人同意が必要で、結果は5年間保存も必要。
実施者または実施事務従業者が行うのが望ましい
通知の際には結果を本人以外が把握できない方法にする
✅実際の面接
面接で確認する事項
当該労働者から
→当該労働者の勤務の状況
→当該労働者の心理的な負担の状況
→当ギア労働者の心身の状況
事業者から
→労働時間や労働密度等の労務の情報
面接後の対応
当該労働者に対して
→保健指導(ストレス対処技術の指導やセルフケア)
→受診指導
事業者に対して
→就業区分の判定(通常勤務 / 就業制限 / 要休業)
→就業上の措置に関する意見
参考:こころの耳(厚労省ポータルサイト) 長時間労働者、高ストレス者の面接指導について
✅高ストレス者への対応
は、①で対象者の意向を確認した後、②~④の対応を行う。
①ストレスチェック実施者から対象者の意向確認
②自己対応(セルフケア)のための資料の提供
③産業保健スタッフ(看護師・カウンセラー)による相談・指導
④就業上の配慮に関する(医師による)面談
産業医として対応するのは④だが
医師の面談に抵抗がある場合は②、③の選択肢をとることになる。

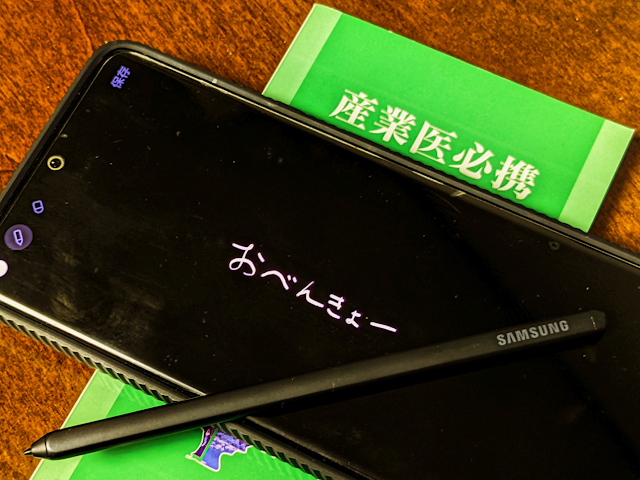
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿
当ブログの内容は端末の文鎮化を引き起こす可能性を伴う危険なものを含み、投稿主は施行の推奨を致しません。
また、このブログコメント欄、Twitter等で問い合わせ頂いても詳細な内容を記載/返答する予定はございません。
自分で調べる。自己責任。転んでも自分で起きる。ことが出来ない方はコメント前にブラウザバックを推奨いたします。